退職金「20年で1080万円減」大きく下がった理由
- 企業・経済
- 2019年4月21日
昭和の時代、定年を迎えるサラリーマンにとって、退職金は「悠々自適な老後」の象徴だった。しかし、平成の30年間でその存在は揺らいできた。額が大きく目減りし、制度のない会社も増えている。【毎日新聞経済プレミア・渡辺精一】
◇5社に1社は「退職金なし」
退職金には大きく一時金と年金があり、受け取り方にも一時金のみ▽一時金+年金▽すべて年金――などのパターンがある。
厚生労働省「就労条件総合調査」は約5年ごとに退職金に関する調査を実施している。それによると、大卒者の定年退職者(勤続20年以上かつ45歳以上)の退職金の平均額は、1997年の2871万円をピークに下がり続け、2017年は1788万円と20年間で1083万円も下がった。
これはあくまで退職金を受けた人の平均額だが「退職金制度がない」という企業も増えた。退職金制度がない企業は93年には8.0%だったが、17年には19.5%に拡大している。規模が小さい企業ほど制度がない割合は高くなる。
◇成果主義や企業年金改革が影響
なぜ、退職金の額が大きく下がり、制度のない会社も増えたのか。理由はいくつか考えられる。
まず、退職金制度の中身が変わったことだ。バブル崩壊後、00年代初頭にかけて、企業の間では、年功的な賃金制度の見直しが進んだ。いわゆる成果主義の導入だ。
退職金の額は、かつては退職時給与に比例して算定する方式が主流で、勤続年数に応じて退職金が増える仕組みだった。しかし、00年代に入ってからは、給与とは別建てにする企業が増えており、特に大企業では「ポイント制」が6割を占めるようになった。
これは、職能等級や役職、毎年の行動や成果などでポイントを設定し、積み上げたポイントに応じて算出する方法で、能力や会社への貢献度を反映させやすい。このポイント制の導入が支給額を押し下げた可能性がある。
退職金額のピーク時からの下げ幅は、大学卒、高校卒ホワイトカラー、高校卒ブルーカラーの順に大きい。ブルーカラーはもともと水準が低いということもあるが、割高だった大卒の中高年への給付を抑制した面が強いことが見て取れる。
制度のない会社が増えたのは、企業年金改革の影響が大きい。中小企業の企業年金の柱は、高度成長期にできた「厚生年金基金」と「適格退職年金」だったが、バブル崩壊後の90年代から金利低下で運用が悪化し、会社は約束の年金資金が準備できない積み立て不足に陥った。
適格退職年金は12年に実質的に廃止。厚生年金基金は、運用詐欺事件が契機となった改正厚生年金保険法(14年施行)で解散や代行返上が進んだ。その受け皿には、積み立て不足が生じる心配のない確定拠出年金が期待されたが、中小企業では運営の負担が大きいことから導入が進んでいない。
もう一つ、定年後の雇用継続が定着したことが関係しているという見方もある。高年齢者雇用安定法改正で06年には定年後の継続雇用も含む60代前半の雇用確保が義務化された。企業は、雇用延長のための財源を手当てしなければならないことになり、退職金の支給額を調整する動きが一部である。
◇3人に1人は「受け取るまで額知らず」
ただし、退職金でこれほどの逆風が吹いているというのに、一般の関心はそれほど高くないようだ。現役世代の多くにとって、退職金の支給は先の話であり、今の給与額のほうが切実な問題だからだ。
フィデリティ退職・投資教育研究所が18年12月、 65~79歳の男女1万1960人に行った調査をみよう。退職金を受け取った人は8055人いるが、退職金の額を把握した時期は「定年退職前1年以内」が63.9%、「退職金を受け取るまで知らなかった」は31.6%もいた。また、68.9%は「会社からの通知で金額を知った」という。野尻哲史所長は「退職金額の把握時期が直前になるほど会社への依存が高い」と指摘する。
これでは老後の生活設計が心もとない。こうしたなか、最近は、退職金のポイントの持ち点や確定拠出年金の資産残高を社員に積極的に情報提供する会社も増えつつある。「会社依存」からの脱却が求められているといえそうだ。
一言コメント
景気拡大を実感できない理由がここにもありそうだ。




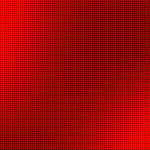












コメントする