特定秘密じわり拡大 施行後4割増の547件 保護法成立6日で5年
- 政治・経済
- 2018年12月6日

政府の安全保障に関する重要情報を守るため、漏えいに重罰を科す「特定秘密保護法」が成立して6日で5年を迎える。法制定時には、秘密の範囲があいまいだとして政府による情報隠しの恐れが指摘されていた。懸念された動きは表面化していないが、識者は「政府内の動きを外から見えなくする仕組みだから当たり前だ。国会などによる監視活動を強化すべきだ」と語る。
特定秘密は外交、防衛、スパイ・テロ防止の分野で、大臣などが指定する。指定は5年ごとに通算30年(一部は60年)まで可能で、秘密を漏らした場合は最長懲役10年が科される。成立の1年後の2014年12月に施行された。
政府の11府省庁が18年6月末時点で「北方領土に関する外国政府等との交渉・協力の内容」など547件を特定秘密に指定。法施行時の14年12月より165件(43%)増加した。秘密を記録した文書は17年末時点で38万3733文書となり、3年間で19万4540文書(203%)増えた。内閣情報調査室の担当者は「増えるのは自然な流れだ」と話す。
日本弁護士連合会などは(1)秘密の範囲が広く不明確(2)官僚組織が自分たちの都合で指定できる(3)重罰で知る権利が侵害される――の問題点を指摘していた。NPO法人・情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は「限られた人にしか秘密を見せないようにして情報統制を強化することが目的の法律で、政府内部で起きていることが見えない仕組みだ。問題が具体的に起きていないからと言って懸念が杞憂(きゆう)だというのは誤りだ」として、秘密の閲覧権限を持つ衆参両院の情報監視審査会の活動に期待する。
特定秘密を扱うには「適性評価」と呼ばれる身辺調査を受ける必要がある。資格を持った人は17年末時点で12万4514人(民間人3013人含む)と15年12月より約3割増えた。適性評価を受ける人は病歴や借金の有無などを申告し、政府から確認を求められた医師は回答する義務がある。日本精神神経学会法委員会の富田三樹生委員長は「医療情報の提供義務は医師の守秘義務の原則を破壊する。また医療機関が情報提供したかどうかを(学会として)把握できないのも問題だ」と課題を指摘する。【青島顕、山田麻未】
◇「知られた情報だったのに…」50年前の元自衛官聴取
「“秘密保護法”適用の第一号」――。50年前の1968年2月29日の毎日新聞朝刊(東京本社版)にこんな見出しが躍った。特定秘密保護法のできるはるか昔。元自衛官が雑誌に自衛隊の米国製戦闘機の性能を載せたことで、米軍の秘密を保護する法律(MDA秘密保護法、54年施行)に違反したとして、警視庁から取り調べを受けたという記事だ。立件はされなかったという。関係者は「米国では既に知られた内容だった」と言い、機密保持を巡る同様な問題の発生を心配する。
元3等空佐の青木日出雄さん(88年に61歳で死去)は66年、雑誌「航空情報」にF104J戦闘機の解説記事を書いた。その中で、レーダーの探知距離など二つの数字を挙げた。それが1年半後に突然、米軍提供の秘密を漏らしたとみなされた。
最初の記事の2週間後、3月13日の毎日新聞朝刊(同)は捜査に疑問を投げかけた。「米軍のトップシークレット(極秘)だったのは10年も昔のこと。なんでいまごろヤリ玉にあげたのか。アメリカに気兼ねしたのか」との軍事評論家の談話を載せた。青木さんはその後、航空評論家としてテレビなどで活躍した。
長男で航空評論家の謙知(よしとも)さん(64)は「父親はホテルに軟禁されて調べられたが、探知距離は米国では知られており、無理筋だった。不起訴になったと聞いている」と振り返る。
MDA秘密保護法は現在もあり、特定秘密保護法を作る際に参考にされたとみられる。謙知さんは特定秘密について「情報が機密なのか確認するすべがなく、(処罰を恐れて)きちんとした情報を伝えられなくなるのが怖い」と話す。【青島顕】
一言コメント
地味ながら運用されてるんだね。







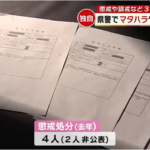












コメントする